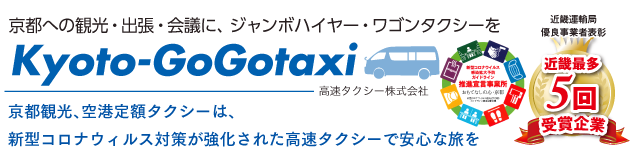防衛する運転
タクシー会社が発信するブログではあまりというか全然お目にかかったことのない「事故」について触れます。
タブー視される事柄の代表ですが、ここは勇気をもってお話したいと思います。
今日は私にしては珍しく結論から言います。
ズバリ、
「タクシー乗務とはこちらに対して向かってくるあらゆるものから避けまくりながら、こなしていく仕事である。」
です。
私がこの仕事に就いたときから「タクシーに事故は付き物。」と言うことを会社から聞かされ続けてきました。
事実、事故は起きます。
その形態は
・第一原因事故 ➡︎双方が動いており過失が発生するもの。及び自損事故
・第二原因事故 ➡︎当方が完全に停止してる状態であるもの。(被追突事故)
に大別されます。
「事故を起こしたくてする者はいない。」わけですが、それでも事故は起きてしまいます。
私は万一起こしても最小限にとどめるにはどういった走り方をしなくてはならないかを考え続けています。
「防衛運転」という言葉がありますが駆け出しのころはあまりピンときていませんでした。
幸いこれまでプライベートも含め人身事故を起こしたことはありません。(空車時に不注意でサイドとかをこすったことはあります)
この仕事をはじめてから2年半くらい経ってようやく防衛運転の何たるかを理解できました。
一番は「速度」
これは道のサイズや交通状況をみて、しっかり緩急をつけると言うことです。
ここで、「遅すぎてもダメ」であることを強調しておきます。
「遅い=安全」と思っているタクシードライバーは一定数存在しますが、遅すぎることで事故を誘発することもあります。
2番目は「危険予知」
「一旦停止」がついてない、いわゆる優先道路でも「横からノンストップのクルマや自転車が来るかもしれない。」と言った「かもしれない。」と思いながら運行できるかどうかが大きな別れめになってきます。
それでもヒヤッとすることは毎日出くわします。
絶えず洞察力を働かせ危険予知、状況判断をすることが重要です。
「事故惹起者」と言う非常に不名誉な言い方をする事がありますが事故を起こすには相応の原因があります。
例えば当方が一旦停止のラインで停まって次に出たタイミングで出会い頭事故と言うのが少なくありませんが、これは完全に防げるものです。
2回目には停止線はありません。しかし横から通行車両があれば当然停まる必要があるわけです。この形態の事故を起こした方は決まったように「止まれで停まったのに。。。」とボヤいてます。
この言葉にこそ「止まれ」の本義本質がいかにわかっていないかが詰まっています。
「止まれ」は「止まることが目的」ではなく、あくまでも事故をしないためにタイミングをずらすためのものであると捉えるべきです。
冒頭の「避けまくる—」を言い換えれば「事故を起こさないタイミングを作っていく。」作業の繰り返しであろうと感じます。
加えて京都市内は原付バイク、自転車が非常に多いエリアであり、最大限の注意を払わなくてはいけません。
私は某国立大学周辺を走行する時は本当にMAXの注意力をもって走ります。
学業は優秀でも自転車の乗り方は極めて横着で、何度もドキッとしたことがあるのです。
さらに私個人としては「徳を積む。」ことも重視しています。
人目がないところで落ちているゴミを拾うとかそういった積み重ねで間一髪を免れることもあるんではないかと思い、かなり前から実践しています。
これらを立証をできる術はありませんが、これからも続けていく考えに変わりありません。
とにかく今日も明日もあさっても、この先もずっと避けまくりながらの安全運行に徹していきます。
掛見